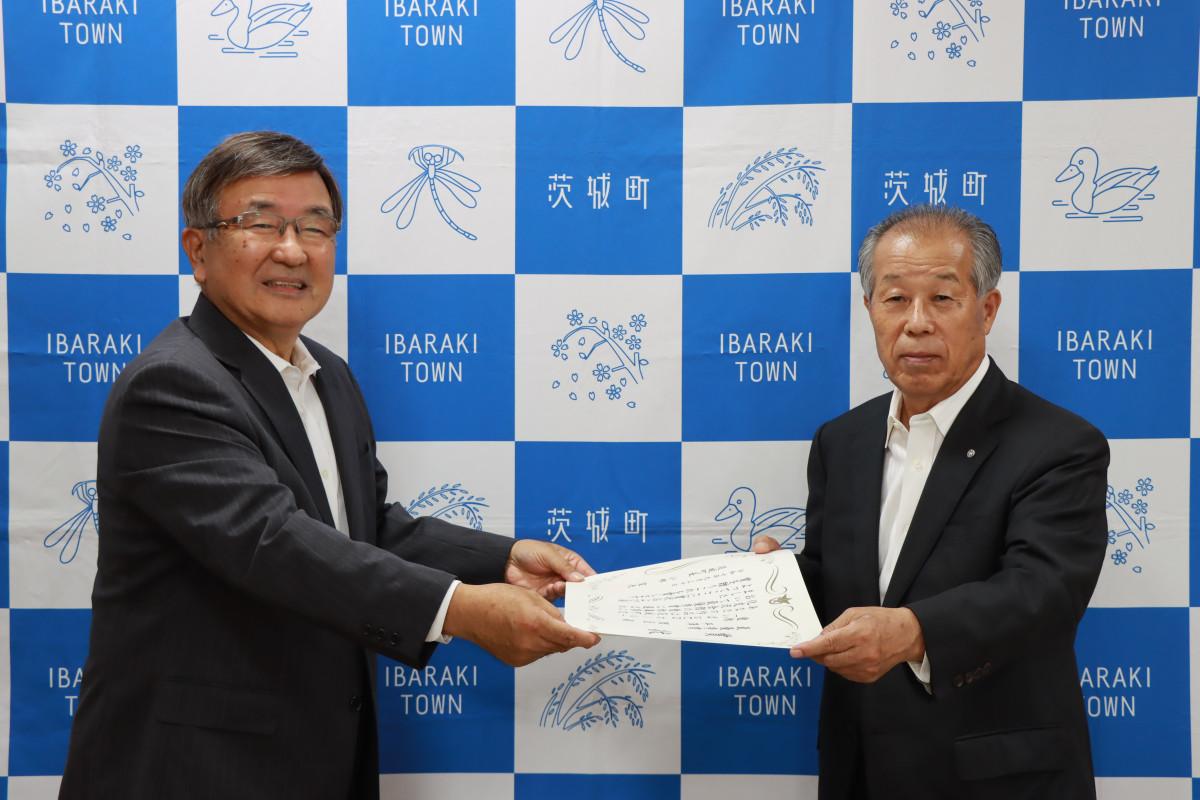料理人団体「常陸国ガストロノミー」が9月29日、レストラン「COLK(コルク)」(水戸市笠原町)で「常陸乃国いせ海老」の料理研究会「常陸国ガストロノミーLAB vol.12」を行った。
(左から)会場で料理を仕上げる「atelico」の新島さん、「L'ame(ラーム)」の加藤大恭さん
2022年に茨城の食文化発展を目指し発足した同団体。「ガストロノミー」はフランス語で「美食学」を意味する言葉で、約2カ月に1回のペースで、団体メンバーの料理人や生産者が集まり、茨城県産の食材をテーマに研究会を重ねてきた。同団体代表の西野正巳(まさみ)さんは「京遊膳花みやこ」(ひたちなか市笹野町)を経営する料理人。「長年の経験と食材への深い知見を生かして生産者と料理人をつなぎ、茨城独自の食文化醸成」を目標に掲げる。
今回のテーマ食材は、大型で濃厚なうまみが特長の茨城県産イセエビブランド「常陸乃国いせ海老」。県内外の7店から8人の料理人が参加したほか、今回初めて設けた一般枠として2人が参加した。参加者はそれぞれテーマに沿った1品を披露し、ほかの参加者に向けて解説。その後、全員の料理を試食しながら食材や調理法について議論を交わした。
参加した「COLK」の大森浩昭さんは「『常陸乃国いせ海老』の大きさと強いうまみ、さらに調理法によって食感や味の表現を変えられることを再発見できた」と話す。埼玉県から参加したレストラン「atelico(アテリコ)」(比企郡小川町)の新島貴行さんは「普段は一人で調理場に立っているので、メンバーの料理から学んだり、生産者と話せたりすることは刺激になる」と話す。
一般枠で参加した矢野りほさんは「普段は親子向けの食育活動などを行っている。ここで料理を出すことは緊張したが、子育てや食育の経験からおいしさだけでなく子どもが食べられることや健康への意識を共有できればと参加した。学び得たことをかみ砕き、主婦の方にも伝えたい」と振り返る。同団体副代表で「鮨松榮」(笠間市東平)店主の臼井幸紀さんは「今後も一般枠を用意してこの団体の活動に関心を持ってくれる人を募集し、徐々に活動を広げていきたい」と意気込む。
西野さんは「日頃から地元の食材同士の相乗効果を生み出したり、自分の料理の勉強をしたりする場にしようという中で、今回もオリジナリティーのある料理が並んだ。情報交換や対話をして切磋琢磨(せっさたくま)し、地域の飲食業の底上げをしていきたい。活動を続けていくことで、茨城の優れた生産者と料理人が一緒になり、茨城の観光事業や食文化がさらに醸成されることにつながれば」と話す。